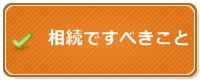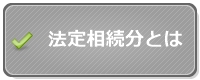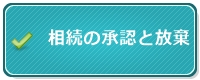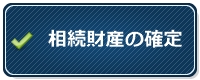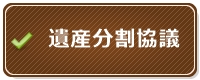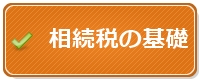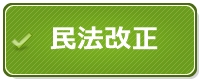相続手続き代行業務

当事務所の基本業務~相続完了まで一切を行います
- 戸籍を含む書類取得、書類作成(相続人確定・相続財産確定)
- 相続人様全員とのやりとり
- 金融機関払戻し、各相続人様への相続金分配、計算書送付
- 相続登記(提携司法書士)、税務申告(提携税理士)
相続業務・遺産分割協議のご相談
相続の最初から最後まで。ご相談承ります
相続に正解はありません。少しでも円満な相続、スムーズな相続、負担の少ない相続を目指しましょう。
故人様の遺言書はありますか。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議を開催する必要があります。相続人が2人だけであっても同様です。また遺産分割協議は相続人全員が合意して、「遺産分割協議書」という書類を作成しなければなりません。これは相続財産はどのようなもので、各相続人がどのように分割配分し、なおかつ最終的にそれに相続人全員が合意したという文書になります。ですので、基本的には相続人だれ一人欠けても成立しません。重要な文書ですので、全員の署名及び実印押印によって完成致します。預貯金払戻や相続登記などは、この書類をもって手続きが進んでいきます。
だれもが円満な相続を望んでいますし、せっかく故人様が残してくれた財産で争いたくはありません。では相続はどのような知識をもって、どのように行っていけばよいのでしょうか。相続は相続人の皆様にとって、心身ともにご負担がかかるものです。特に中心となって手続きを行われる、代表者の方にとってはなおさらです。しかし相続はいやでも避けては通れませんし、限られた期間内に手続きを行う必要があります。
トラブルに至る前に、スムーズな解決のお役に立つことをお約束いたします。
葬儀後の手続きの確認
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい
葬儀後の手続きは完了していますか。詳細は市町村等に確認下さい。
葬儀後速やかに
- ■市町村役場
- 遺族基礎年金の請求(国民年金)
- 葬祭費の請求(国民健康保険)
- ■社会保険事務所
- 遺族厚生年金の請求(厚生年金)
- 埋葬費などの請求(健康保険)
- ■労働基準監督署
- 遺族補償年金等の請求(労災保険)
- 葬祭料の請求(労災保険)
- ■税務署
- 死亡者の所得税確定申告
- 医療費控除の還付請求(税金)
- ■勤務先
- 死亡退職届の請求
- 扶養控除異動の届出
- ■各契約会社
- 口座振替の名義変更
- クレジットカードの退会届け出
- 保険金の請求
- 電話の名義変更
- 借地・借家の名義変更
- 賃貸住宅の名義変更
遺産分割協議成立後
- 相続した預金、貯金の支払い請求
- 預金、貯金の口座名義変更
- 株式、債券の名義変更
- 不動産の名義変更
- 自動車の移転登録
- 相続税の申告
相続とはどういうもの

相続とは被相続人(亡くなられた方)の有する財産上の一切の権利義務を、特定の者に承継させることをいいます。ただし権利義務には、個人の資格や役職であるとかの、いわゆる一身専属的な権利は含みません。またプラスの財産(土地や現金・預貯金等)だけではなく、マイナスの財産(負債や借金等)も含みます。
相続には被相続人の遺言による「遺言相続」と、遺言等がない場合に、民法の規定に基づいてなされる「法定相続」があります。「遺言相続」も民法に条文化されており、前述のように明確な方式が規定されています。
遺言書ではプラス財産の配分のみ記載され、マイナス財産の配分が記載されていない場合も多くあります。しかしマイナス財産は、プラスの相続財産を相続しなかったとしても、裁判所ですべての財産を相続放棄しない限りは、相続人全員に必ず法定配分されます。例えば配偶者の場合では、渡されるプラスの財産が遺言や遺産分割協議によって仮に総額の4分の1であったとしても、マイナス財産は必ず総額の2分の1の割合で配分されますので注意が必要です。連帯保証の債務も割合に応じて当然に承継されますので注意が必要です。
相続の開始について
相続は被相続人の死亡により、被相続人の最後の住所地において開始します。
相続の効果は、すべての財産が承継される「包括承継」となります。通常は遺言書に記載された遺言執行者の方や、最も相続財産が多いと思われる方が代表相続人として、中心となって相続を取り進めていきます。しかし、複数の相続人がいる場合は各自が「共同相続人」となり、相続人全員で協議をまとめることで相続が行われます。代表相続人の一存で決めることはできません。
相続には承認や放棄の期限(3ヶ月)、納税期間の期限(10ヶ月)などが定められており、この期限を過ぎてしまうと様々な権利を失うこととなりますので、注意が必要です。
トラブルに至る前に、ご家族円満のお手伝いをさせていただきます
故人様の遺言書は残されていますか。相続とは、故人様の遺産を相続人の方々に分配する手続きになりますが、遺言書の方式に基づいて作成された遺言書(法的効果のある遺言書)があれば、基本的にはその内容に従って手続きを行っていくことになります。しかしそのような遺言書がなければ、相続人全員で遺産を分けなければなりません。
相続は法律にも定められており、税金も絡んできますので、期限内に行わなければなりません。段取りをふんで、早期に円満な相続を済ませましょう。
相続の最初から最後まで。ご相談承ります
自筆証書遺言書が残されていた場合の段取り
- 封を開けずに、家庭裁判所に「検認」手続きを申し立てます。誤って開封してしまった場合でも、必ず「検認」手続きは受けましょう。
- 万が一自筆遺言書を遺棄したり改ざんしたりした場合は、相続人としての権利を失うこととなります。どのような場合であっても行ってはいけません。
- 検認とはその遺言書が確かに存在していることを確認し、改ざん偽造されることを防ぐ目的で行われます。
- 相続人ひとりから検認の申し立てがあった場合は、他の相続人全員に検認を行う旨の通知が届きます。
- 検認に参加された相続人全員で検認に立ち会います。検認に欠席されても、相続人としての地位がなくなるわけではありません。
- 検認は遺言書の署名や日付等の形式を確認するものであって、遺言自体の有効性の可否を判断する手続きではありません。
- 検認後に各相続人(あるいは専門家に依頼し)で、その遺言書が法律効果があるかを確認します。
- 法律効果がある場合は基本的に故人の意思に従います。
- 法律効果がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。法律効果が無い遺言書(民法の形式に則っていない自筆遺言書)であっても、相続人全員がその内容に合意すれば、遺言書の内容にしたがって相続を行ってもさしつかえありません。しかし一人でも内容に異議を唱えれば、その遺言書は法律的な効果を発揮しません。
遺言書の法律効果や真偽の確認をしますが、法律効果がある遺言書でも相続分に偏りがあった場合などは、遺留分の問題が生じる可能性があります。
公正証書遺言書が残されていた場合の段取り
- 遺言執行者が記載されている場合には、その方が故人様の意思に基づき相続手続きをとりおこないます。遺言執行者は民法により強い権限が付与されており、他の相続人の委任状などがなくても、相続を執り行うことができます。
- 遺言執行者が記載されていない場合には、通常は相続分の一番多い相続人等が代表相続人となり、相続をとりおこないます。
- 遺留分が発生する場合や、他に法定相続人がいる可能性がある場合は、念のために戸籍をたどって相続人調査を行っておいた方が安心です。
- マイナスの財産の方が多い懸念がある場合は、事前に財産調査も行っておいた方が安心です。
- 遺留分が請求された場合は、基準に基づいた請求額を支払う必要があります。
- 公正証書遺言が残されている場合でも、別途相続人全員の協議が整った場合には、その協議の内容を優先することも否定されません。その場合でも必ず、遺言書に記載されている遺言執行者との打ち合わせを行いましょう。遺言執行者には、遺言とおりに相続を行う義務があるからです。
公正証書遺言の場合は、方式に問題はなく内容は精査されいると考えられますので、段取りを踏んで手続きを行っていきます。
遺言書が残されていない場合の相続の段取り
- たとえ遺産分割協議が成立したとしても、遺言書があとから出てきたときには、協議をやり直さなければいけない場合があります。遺言書に記載された、特定の相続人の相続分が多かった場合などです。まずは遺言書を探しましょう。
- 財産関係をすべて調査します。プラスの財産だけではなく、必ずマイナスの財産も調査しましょう。
- 相続人関係をすべて調査します。知れていない相続人も含め、すべての関係する戸籍から相続人を特定します。
- 代表相続人が共同相続人全員に連絡をとり、遺産分割協議を行います。
- 遺産分割協議の成立には、相続人全員の参加と相続人全員の合意が必要となります。
- 相続の承認や放棄、相続税の納付などについては期限があり、この期限までに協議が成立しないと税の特例が受けられません。
- 遺産分割協議書に基づいて、金融機関や法務局への各種届出が必要となります。
- 協議が整わない場合は、原則金融機関からの払戻しや不動産登記などが行えません。その場合は家庭裁判所の調停等が必要となります。

次の内容に思い当たる方は、遺言を残さないと相続がもめる原因になります。遺言書作成は家族を思われるあなたの義務です。
ひとつでも思い当たることがある方は要注意。
- 財産の大部分が不動産(土地、建物)
- 配偶者をこのまま自宅に住まわせてあげたい
- 事業を継がれる方に財産を多く残したい
- 配偶者はいるが子供がいない
- 相続人が兄弟のみ
- 相続人が多い
- 相続人がいない
- 事実婚の相手がいる
- 家族以外に知られていない認知した子供がいる
- 再婚した配偶者に認知していない子がいる
- 相続人が行方不明であったり海外にいる
- 相続人どうしが疎遠であったり不仲である
- 特定の家族に財産を多く残したい
- 相続人以外の者に財産を譲りたい
- 生前に援助した子供に額の差がある
- 介護してもらっている特定の親族に多く残したい
- 財産を残したくない相続人がいる
- 自分の死後に気がかりなことがある

■令和3年度遺言作成件数(全国)
●死亡者数 1,399,158人
●公正証書遺言 106,028件
●自筆証書遺言 18,277件(令和2年度)
*自筆証書遺言の件数は令和2年度の家庭裁判所への検認申立件数であって作成された実数は不明です。
*それでも公正証書遺言は年間これだけ作成されています。
相続は嫌でも始まります
相続には心身ともにご苦労が伴います。でも相続はいやでも始まります。
トラブルに至る前に、相続人みなさんが今後ともご円満でいられるように、より良い形での相続業務を承ります
このページを読まれた方は、次の記事も読まれています。
当事務所のお役立ち
当事務所にご依頼いただくメリット
- 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
- 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
- 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
- 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
- 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
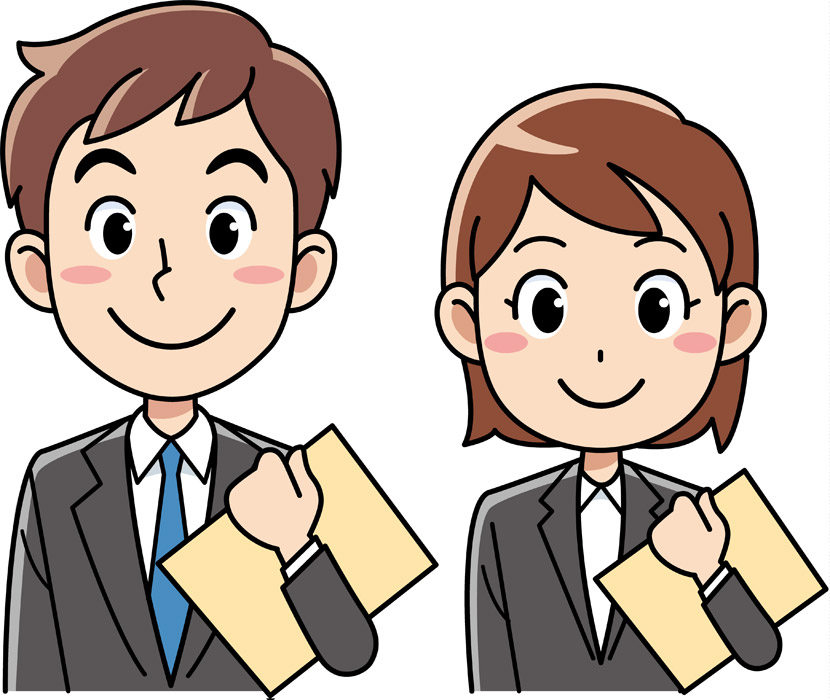
行政書士の仕事と当事務所のお約束
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
- お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
- 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。
書類の作成や文書の作成などは、

- 法律や申請方法を勉強し
- 数々の書類を取得し
- 慎重に書類を作成し
- 平日に役所と交渉をし
- 平日に役所に申請をする
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
行政書士と他士業
- 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
- 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
- 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
高崎市新保町329番地3
高崎インターから5分
℡ 027-377-6089